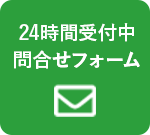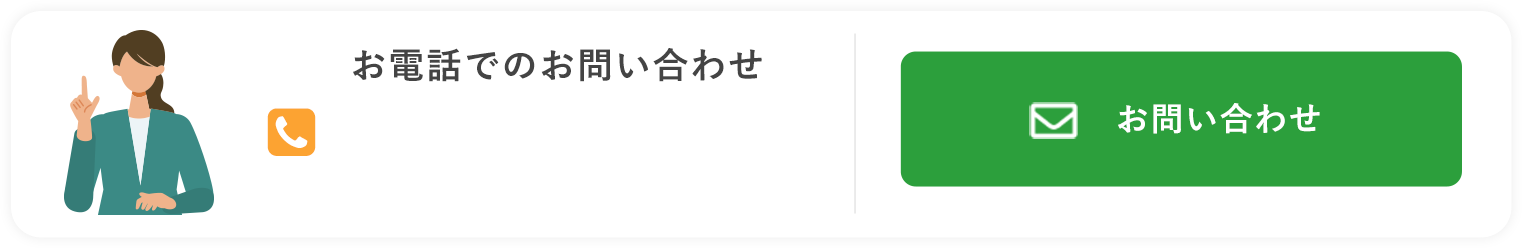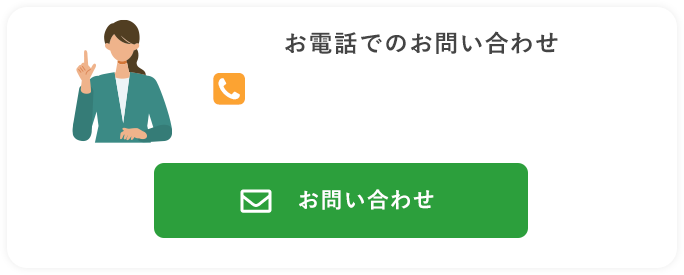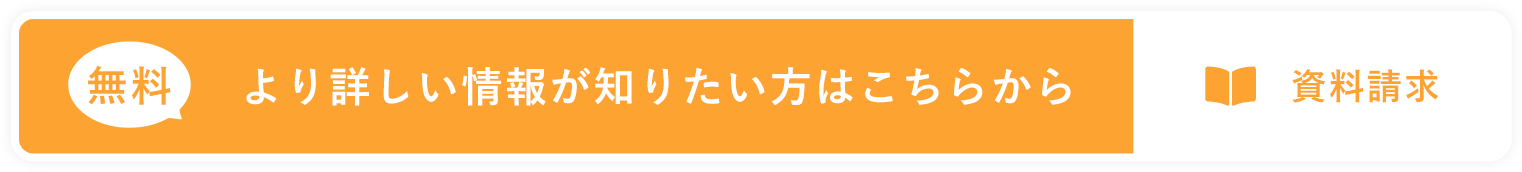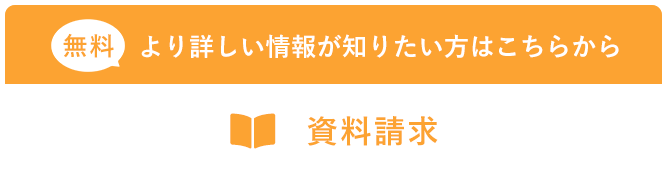【令和5(2023)年10月施行】インボイス制度の対応方法や経理への影響を徹底解説

正式名称:適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が令和5(2023)年10月にスタートしました。 会社で何をするべきなのか、何をチェックしていかないといけないのか、簡単にご説明します。
インボイス制度とは
インボイス制度とは国税庁の概要説明によると―適格請求書(以下インボイスとします)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの 具体的には、令和5年9月30日までに使われていた区分記載請求書に
①登録番号 T+13桁の数字
②摘要税率
③消費税額等
これらの情報が追加された書類やデータをいいます。
売手側の対応:買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならず、また、写しを保存しておく必要があります。
買手側の対応:仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
インボイス制度の対応方法
課税事業者がインボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者(以下、インボイス事業者とします)になる必要があり、納税地を所轄する税務署に登録申請書を出し、登録を受けます。 また、もともと免税事業者だった場合、インボイスを発行できるように課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかを選択する必要があります。 課税事業者になってインボイス事業者の申請をすれば、インボイスを発行できることになりますが、それはイコール消費税の申告義務が発生することとなり、今まで所得税の申告だけで済んでいた個人事業者や、法人税の申告だけでよかったところ、消費税の申告も併せて行う必要が出てきます。税理士事務所・税理士法人と契約をしている場合、消費税の申告の料金は別途かかるところがほとんどかと思われます。 金額面や手間の面を含め、免税のままでいるメリット・デメリットと、インボイス事業者となって課税事業者となるメリット・デメリットを充分に比較されることをお勧めします。 また、自社で仕訳入力を行っている(自計化されている)場合、使っている会計ソフト・システムの変更点にも留意する必要があります。場合によっては、バージョンアップなども必要ですので、インボイス制度に適した会計ソフト・システムになっているかご確認ください。
インボイス制度による経理への影響
インボイス制度の事前準備やスタートで経理がチェックすべき点が増えています。
①インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者(以下、インボイス事業者とします)として課税事業者になったケース:特例として仕入税額控除の金額を特別控除税額とすることができることになりました。具体的にこの特例を適用すると、売上税額の2割を納付することになります。この特例にも期限があり、令和8(2026)年9月30日までの日の属する課税期間となっています。適用可能な事業者にも要件があり、「基準期間の課税売上高が1000万円以下のインボイス発行事業者」が対象となっていて、注意が必要です。ここでいう”基準期間”とは、 個人事業者の方では前々年、(令和5年度で考えると令和3年)、 法人であれば、前々事業年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日の事業年度で考えると令和3年4月1日~令和4年3月31日の年度) を指しています。
②基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間※における課税売上高が5000万円以下の事業者のケース:令和5(2023)年10月1日~令和11(2029)年9月30日までの間の課税仕入れについて、税込で1万円未満であるものについては一定の事項を記載した帳簿のみを保存することでインボイスの保存がなくても仕入税額控除が可能となりました。この「税込1万円未満」に該当するかどうかは、1回の取引の課税仕入れ金額が税込1万未満であることが必要です。
例1) 10/1に 5,000円の商品仕入、10/10に 15,000円の商品仕入を行った
→税込1万円以上となる10/10のインボイスの保存が必要 例2) 10/25に 5,000円の商品と6,000円の商品仕入を同時に行った→税込1万円以上の取引となるため インボイスの保存が必要 このように金額を確認し、保存するかしないかを確認していく必要が出てきました。
③適格返還請求書(返還インボイス)
※特定期間とは・・・個人事業者の方であれば、前年の1月~6月 いわゆる上半期、法人であれば、原則として前事業年度の開始の日以後6か月・いわゆる前年度上半期
まとめ
ここまでインボイス制度の対応方法や経理への影響についてお話してきました。インボイス制度は複雑になっており、どのように対応すればよいかわからないといったご相談を多く受けます。ぜひインボイス制度への対応や今後の経理への負担でご相談や不安なことがある方はお気軽にお問い合わせください。